尾向の風
■ 交流会
まだまだ梅雨明けしないですね
7月8日の交流会、天気が心配されたけど
土曜日の昼から雨も上がり
8日の日曜日は晴天。。。ビール日和でしたね\(^o^)/
勝手に交流会名変更
七夕交流会
樅木・向山地区交流会
毎年7月に行いお互いの地区の人が1年に1回の再会を楽しみにしています
まず10時から峰越林道を県道昇格を願っての促進期成会の総会(写真なし)
11時から公民館で交流会の開会式

日当中組長さんの司会進行で開始です


向山区長さんの挨拶 樅木区長さんの挨拶


浄信さんによる経過報告 みんな真剣に聞いていますね


入りきれん程いっぱいですね 天気になってよかったなーい!!


椎葉村長さんの挨拶 八代市副市長さんの挨拶
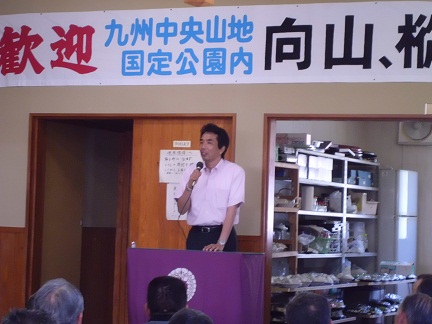

江藤代議士の挨拶 金子代議士の挨拶
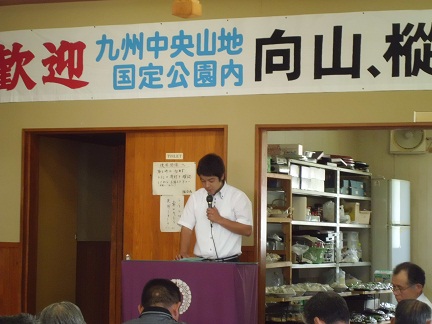

尾向青年副会長による声明文朗読 みなさん長らくお待たせしました
乾杯といきますよー\(^o^)/

あー腹減っとったからなー
冷たいビールがうまぁーごたる(゚д゚)ウマー

1年ぶりじゃね 元気じゃったかい
子供もふとーなったない(*´∀`*)

台所の婦人会は忙しそうだね お先にいただきますよ(´ー`* ))))

私たちもお世話になるねえ( ^ω^ )ニコニコ
いえいえこっちこそよろしくお願いします
出番は、、、、、、、じゃから、、、、( ; ゚Д゚)( ; ゚Д゚)アセアセ
と 七夕交流会は始まったのであります
続きは後日に( ̄ー ̄)/~~

これは記念写真、、、先にアップしてしまいました( ´・ω・`)ノ~(´ー`)/~~
12/07/19
■ カエルの子はカエルでしたヽ(*´∀`)ノ
梅雨の中休み、、、ほんの3日ヽ(τωヽ)ノ
経験したことない大雨が降ったようです
熊本・大分の災害は想定外、、、の大雨
ニュースを見ていると涙が出てきます
もうこれ以上降らないで欲しいですね
向山川も朝起きた時の川はまだ綺麗な色で流れていたが
午前中の大雨で一気に増水し、黒濁りして流れている
6月下旬の大雨の時よりも増水しました
熊本が大降りすると、尾向も大降りするので気をつけないと
昼に雨が止むと川の水は減りはじめ茶色くなってきました
でも下流域は降った雨が全部流れていくので
水量は増えるかもしれないですね。気をつけてください
約30年前の7月下旬 日当倉の迫で集中豪雨のため
土砂災害があり2名の方が犠牲になりました
その時の雨量が400m近く降ったとか、、、、
真っ暗い空からの雨、雷様と、、、、恐ろしかったのを覚えています
この時も「こんな雨初めて」との声が聞かれました
この頃から集中豪雨・ゲリラ豪雨という言葉が聞かれるようになり
全国的に豪雨の災害がいたるところで発生するようになりました
そして雨ばかりでなく気温が高くなったり、台風の進路が昔とちがったり
雪が降らなかったり、雪が多すぎたり、、、、
それを」異常気象と言うようになりだいぶ経ちますが
益々異常気象が続きそうですね
まだまだ雨は続きそうです
車での行き通り気をつけてください
田の水や川の水を見に行かないようにしましょうね
☂ ❀ ☂ ❀ ☂ ❀ ☂ ❀ ☂ ❀
♪ かえるのうたが きこえてくるよ
クワクワクワクワ
ケケケケ ケケケケ クワクワクワ ♪
4月下旬に田の代開けを終えると
どこからともなく聞こえ始め
うるさいと思っていても、いつの間にかおとなしくなっている
だんぼのどこそこでカエルの卵らしきものが、、、
あれから2ヶ月どうなったかな(「・ω・`)・・・ドレドレ
6月23日の写真

田植え後約40日 ちゃんと育ってるね

あれ〜 びきの子じゃないかあ (オタマジャクシとも言う)



(*^・ェ・)ノ コンチャ♪ 水面をパクパクしちょるよ
カワ(・∀・)イイ!! というより むぞうなね(*´∀`*)
これくらいの時はまだ逃げ足が遅いので
手ですくえるっちゃが ○○⊂(゚∀゚*)
大きくなったら何になるっちゃろう(´ε`;)ウーン…
わかってるくせにー<(`^´)>

イモリさんもいるッちゃが ひっくり返ると赤腹だよ
ヤモリさんに似てるね(^0^)/
♪ オタマジャクシは かえるのこ
なまずのまごではないわいな
それがなによりしょうこには
やがて手がでる 足がでる ♪
梅雨の雨の切れ間にまたカエルの合唱が聞こえてきたよ
久々のほんの一っ時の晴れ間に覗いてみたよ(「・ω・`)・・・ドレドレ
7月6日の写真

カニさん ´ω`)ノ コンニチハ

見ゆるどうか、、、、、、、、、、、緑色の体に黒いしっぽ
後ろ足もはっきりわかるどう\(^o^)/

(@_@。オヤオヤ アメンボさんも写りたかったとね ┐(´∀`)┌ハイハイパチリ
びきの子がカエルになる瞬間じゃったですよー
まだまだびきの子、カエルになりかけの子、カエルの一歩手前の子
そしてはっきりとしたカエルが、、、、、、
そこらじゅういっぱいおるけど、撮れませーん
みんな逃げ足が早えっちゃが
脚力ついたっちゃろうね
そして夜は挨拶に来てくれたッちゃが
( ノ゚Д゚)こんばんわ〜

ガラスにはみつくこの姿、、、

へへへ 僕でした (アマガエルでいいのかな)
明かりに来る虫を食べに来ているよ(゚д゚)ウマー
近頃はカエル少なくなったようにかんじるけど、、、、
びきの子はあんげいっぱいおるとに、、、
特に大きなガマさん見かけなくなったな〜
夏になると、夜は軒下にいてびっくりしてたよねΣ(´∀`;)
シロゴマ 暑い時はひる寝の場所さがしがたいへんにゃー(=‘x‘=)

この帽子素敵だにゃあ

流しの中に頭がおつるよ、、、、1時間くらい眠ったシロゴまでした(=‘x‘=)
7月8日の樅木地区との交流会無事終わりましたよ〜
その時の模様は後日アップしますね( ̄ー ̄)/~~
12/07/12
■ 手作りこんにゃく

6月3日撮影
土曜日からバケツで汲んでかやすような大雨
雷様までゴロゴロ
川の水もあっという間に増え黒濁り
道路の崖崩れも所々に
大きな災害にならないでよかったですね
「ハゲ水」 半夏生に降る大雨のことだそうです
これが過ぎると梅雨も明けると昔の人は言うけど
今は異常気象の時代、、、、早く明けるといいですね
半夏生:7月2日頃(2012年は7月1日)。夏至から数えて11日目頃。
今日は叔母の家でのこんにゃく作り を(6月3日)

こんにゃく芋です

大きいですね

茹でてから皮を剥き、ミキサーにかけます
皮をきれいに剥くので黒っぽくなりませんよ

水を入れながら混ぜてのばします(力のいる仕事ですね)

灰汁を入れてまたまたよくかき混ぜます
綺麗に混ざるまで何度も何度も混ぜていました
(私の母は、手首の腱鞘炎を起こしたことがあります)

手に水をつけながら表面を平らにします

手で丸く形作ります

沸騰している窯に入れて茹でます

1窯で50個くらいできるそうです

火は絶えず焚いておきます

中までしっかり煮えるように1時間近く煮ます

出来上がりました。自然に冷めるのを待ちますよ
灰汁(アク)がないとこんにゃくはできません
叔母は下記のように作ります
ポリ容器の上にざるを置き新聞紙を敷く。木灰を入れ熱湯を注ぐ
滴り落ちた液体が灰汁です
木灰は堅木のものがいいそうです
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
こんにゃくはどのように作られるか
●マンナンが固まる性質を利用
こんにゃく特有のプリプリとした歯ざわりは、こんにゃくに含まれるこんにゃくマンナンという食物繊維が灰汁(あく)というアルカリ性物質によって変化したためです。
昔は、こんにゃく芋を生のまま、あるいはゆでて皮をむいてすりおろしたものを使うのが主流でしたが、今ではこんにゃく芋を薄く切って乾燥させ(荒粉・あらこ)、さらに細かい粉(精粉・せいこ)にしてから作る方法が主流になっています。これはすでに1700年代に常陸の国(今の茨城県)の中島藤右衛門が発見した方法で、この加工法によって一年中こんにゃくを作ることが可能になりました。こんにゃく芋はとても腐りやすかったため、この方法が発見されるまでは、こんにゃく芋が収穫できる秋限定の食べ物だったのです。
灰汁でアクを抜くのがミソ
こんにゃく芋は、少しかじっただけでも口の中がピリピリするほどの強烈なエグミがあり、他の芋のようにそのままゆでたり、焼くだけでは食べられません。
エグミの正体はシュウ酸やフェノール誘導体など、これらを中和して取り除くために必要なのが、こんにゃくを固める働きもする灰汁(あく)です。誰が思いついたかは定かではありませんが、アクを灰汁で取り除くという先人の智恵には脱帽です。灰汁には、昔は草木灰が使われていましたが、最近では消石灰(水酸化カルシウム)や炭酸ソーダ(炭酸ナトリウム)が使用されています。使用量は、消石灰なら、生いもの重さの0.5〜1%(精粉の場合は重さの約6%)が目安です。しっかりとアクを抜くためには、固めたこんにゃくを30分〜1時間ほど煮てから十分に水にさらすことが肝心です。なお、生のこんにゃく芋500g分で板こんにゃく5〜6枚を作ることができます。
http://www.konnyaku.or.jp/dekiru/f_dekiru02.html
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
手作りこんにゃく、刺身にして食べても
煮つけて食べても美味しいですよね
こんな美味しいものが食べれる幸せ(´ー`* )))) あ〜ん♪
だけど作る人がどんどん少なくなっているような
我が家の畑にもこんにゃく芋が芽を出しているが
果たして私に出来るでしょうか(´ε`;)ウーン…、、、、、(ヾノ・∀・`)ムリムリ、、
ちょっと
ちょっと
(((‥ )( ‥)))キョロキョロ
ちょっと
ちょっと、ちょっとおばさん
(((‥ )( ‥)))キョロキョロ 誰か呼んだかな?

ちょっと おばさんU ゚ _・゚>
えっ わたしΣ(´∀`;) (`ζ.´)オバサンネ、、アタッテマス

いつもきとるけど、僕に挨拶なしだわん▼・ェ・▼
おみやもないし、、、
ごめんね<(_ _)> 小太郎くん
おばさんちょっとばかし 犬さん苦手じゃッちゃが○┓ペコリ
12/07/03
■ もうひとつのイベントヽ(*´∀`)ノ
樅木地区・向山地区交流会
水無から向山日添を通り峠までを峰越林道と言います。
前村長時代に泉村樅木地区と全面開通しました。その以前ずーと昔から交流はあり、ぼんさん道路と熊本では言っていたようです。樅木地区の人は椎葉の人を「那須の方の人」と言います。椎葉までは源氏が追いかけてきたことを証明していますね。
全面開通したことで車での往来も楽になり、観光客も通るようになりました(冬は雪で通れないことも)
両地区の交流会も今年で11回になりますが、16年の台風災害で、通行ができず3〜4年実施されませんでした。21年に向山地区から再開され、22年は口蹄疫で中止、23年は樅木地区で開催されました。
そして今年は向山地区で7月8日(日)に開催されます。
向山審議委員会、婦人会はそれに向けての準備をしています。お互いの地区民ばかりでなく議員さんやお役人さんも多数参加総勢200人くらいになるかも、、、。アトラクションの準備も、、、、
平成21年の交流会(向山で)の一部をちょっと
趣旨
九州中央山脈国定公園をはさんで、東西に位置する泉町もみ鬼畜と椎葉村向山地区は、ともに平家落人の里として800年の歴史を持つ緑の深い山村である。峰越林道が開通する昔から、先人の交流は盛んに行われていた。
峰越林道開通後は、山林に安らぎを求め多くの人が訪れるようになったが、21世紀になった現在、山村は過疎化・高齢化、さらに後継者の問題、嫁問題が山積みしております。そのために山村と都市との交流は不可欠であり、道路網の整備や観光開発をすることによって、若者が定住する豊かな地域づくり及び人づくりを目指すこととする。
記念写真(全員で撮れなかったのが残念)


23年交流会(樅木地区で)


交流会が始まった頃は、地区民が主だったので
グランドゴルフ等もして楽しんだ事もあります
お互いの神楽を披露したり、歌に踊りに、、、
また子供たちも参加しています(^-^*)(・・*)(^-^*)(・・*)
ちょっと峰越峠まで(県境峠だよ)ε=(/*~▽)/ε=┌(;・∀・)┘イッテミヨ!!
秘境ルート開通の碑
峰越連絡林道椎葉・五家荘線
1981〜1986年、5年の歳月をかけて開通しました
椎葉村の案内板
風化され全く案内板の機能なし( ;∀;) カナシイナー
尾向森林郷の説明版は悲惨な状態になっていたよ〜〜(ノД`)シクシク
開通して26年、これを機会に峰越峠も新たになれるといいね
泉村の案内板
八代市に合併し今は泉町、、、、立派な案内板\(^o^)/
こんなのもありました
標高は、、、、、、書いてないよーー(つд⊂)
調べてみたら....〆(・ω・。)。。。。。1,480〜1,500m
樅木まで日添公民館(峰越の館)から車で40〜50分かかります
ここで五家荘をちょっとご紹介\(^o^)/
❀ ☂ ❀ ☂ ❀ ☂ ❀ ☂ ❀ ☂ ❀ ☂ ❀ ☂ ❀
五家荘(ごかのしょう)
1300〜1700m級の九州山地の奥深い位置に点在する五家荘は八代市泉町(旧:泉村)の中の旧村であった椎原、仁田尾、樅木、葉木、久連子の5つの集落の総称であり、五家荘という地名では地図に載っていない。
五家荘地方は平家落人伝説の残る九州中央山地の奥深い山間に点在する集落で九州の秘境と言われている場所である。五家荘にある「平家の里」の資料館には平家落人伝説の資料が展示してある。
その五家荘の中でも一段と山間に入った所にあるのが樅木地区であり、ここには険しい谷間にかかる樅木吊橋がある。昔は地元の集落の唯一の道であり、藤のツルや丸太や竹で出来ていたが、現在は観光名所となっており吊橋はロープで丈夫にできている。
樅木吊橋の近くの高台に「平家の里」がある。入口には茅葺屋根の民家がならび、その先には朱色が鮮やかな神殿造りの平家伝説館や能舞台などがあります。資料館では平家の落人にまつわる伝説や当時の暮らしぶりなどを紹介しています。

(平家・緒方家の屋敷) (地頭・左座家の屋敷)
《 平家・緒方家の屋敷 》
文治元年(1185)3月、壇ノ浦の戦いで敗れた平家一党の内、左中将平清経は入水と見せかけて四国の伊予今治の阿波国祖谷に逃げた。さらに追っ手を逃れて豊後舞鶴を経て湯布院に入り竹田領の士族緒方氏の招きで、しばらくその館に居住。その後姓を緒方と改め九州脊梁の白鳥山(泉村樅木)に住みついたといわれている。
その後白鳥山も手狭になり、その子孫である緒方紀四郎盛行が山を下りて、ここ八代市泉町椎原に住み代々この地を支配したといわれている。
今残っている家は280年前に建造された家である。
《 地頭・左座家の屋敷 》
藤原一族によって九州に左遷させられた菅原道真には2人の子供があったが、道真の死後この2人の兄弟の仕返しを恐れて藤原一族は兄弟を討ち取るため九州に軍勢を差し向けた。その情報を耳にした兄弟は改名して逃げ、ここに住み着いたといわれている。923年頃の話である。

(せんだん轟) (梅の木轟)
《せんだん轟》
五家荘では、昔から滝のことを轟(とどろ)と呼んでおり、名称の後に轟の文字が付くのが普通である。栴檀轟(せんだんとどろ)は落差70m、幅3〜4mで、滝つぼは4mもある大瀑布である。滝の周辺は広葉樹が多く秋の紅葉は特別きれいである。
《梅の木轟》
五家荘で一番有名な滝は上の「せんだん轟」であり、次に有名な滝が「梅ノ木轟」で落差は38mである。この滝は永い間行く道が無く幻の滝と言われていたが、1989年に「梅ノ木轟公園吊橋」ができて観光客でも簡単に行けるようになった。行くまでの途中にも小さな滝がいくつかある。
http://www.yado.co.jp/kankou/kumamoto/kumanan/gokanosyo/goka...
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
他にも見るとこがいっぱい。子供が小学生の時は子供会での1泊キャンプ、
児童館の親子遠足で鹿公園、、、、と思い出いっぱいです(´ー`)/~~
向山のイベントのために
おつるちゃんも来てくれるそうです
みんな会えるの楽しみにしているよヽ(*´∀`)ノ
こうして見ると椎葉村て広いですね
自分が住んでいるとこ分かりますか?(「・ω・`)・・・ドレドレ
12/06/28
■ 扇山々開き(5/13)
台風4号 椎葉を避けて通り過ぎましたね
でも直撃した地域は大変ですね
これからが台風シーズン
備えはちゃんとしておきましょうね
先月の13日の扇山々開き、もう30回になるんですね
私は山開きが始まる前に一度だけ登ったことがあります
登山入り口はもっと下だったような、、、
あいにくの小雨で頂上からは何も見えなかった記憶があります
上りはよかったけど下りは膝が笑い(≧∇≦)
翌日は筋肉痛☆⌒(>。≪)
尾向小の緑の少年団で子供たちも登っていたけど
いつも父親が一緒で、私はパス、、、、
扇山々開き

天気が良いとこんな景色が見られるんだよね
向こうの山はどこじゃろうかね

山登りの安全を祈願します<(_ _)>

村長さんの挨拶(*´∀`*)

緑の少年団を代表しての挨拶(^-^*)(^-^*)

テープカット 村長さんと一緒でニコニコだね(´∀`*)(n‘∀‘)η

尾向小学校 緑の少年団 との記念写真

さあいくぞ━━━━!!ε=(/*~▽)/ε=(/*~▽)/
こんな道らくしょう楽勝だね( ̄ー ̄)/~~

(「・ω・`)・・・アレアレ みんな下向いて無口だね、、、、(゚д゚)(。_。)┐(´д`)┌

[´Д`]オー先頭きってるおじちゃん ワイルドだぜえー
さあーみんなも元気出して続けよー\(^o^)/

┐(´∀`)┌ハイ記念写真です。。。お疲れ様
(・3・) アレー校長先生がいないぞー
(^o^)/ハーイみんなこっち向いて━━━━!! 校長先生はカメラマンだよ(^_-)-☆

(*^^)v(*^^)v(*^^)vイエ━━━━!!イ

小さく(*^^)vイエ━━━━!!イ

山登り。。。。。やっぱー弁当じゃろー(´ー`* )))) あ〜ん♪

今年はシャクナゲがほとんど散っていたようですね
写真は校長先生とPTAの方にいただきました
ありがとうございました_(_^_)_
シャクナゲの花↓私の家のしゃくなげで我慢してね(´ー`)/~~
https://www.vill.shiiba.miyazaki.jp/blog/index-itemid=780
扇山
昭和54年に開催された「第34回日本のふるさと宮崎国体」山岳競技に使用されて以来、白岩山と結ぶ縦走コースとして県内外の登山愛好者に親しまれている椎葉を代表する山です。五ヶ瀬町からの霧立越ルートを南下した九州山地国定公園のほぼ中央に位置します。頂上付近には、シャクナゲの群生地が広がり登山者を癒してくれます。また、松木登山口から登ると8合目付近に山小屋がありいつでも休憩がとれます。ブナやヒメシャラ、ミツバツツジやシャクヤクなども生息する動植物の宝庫として有名です。
鹿野遊の内の八重からのコースもあります。
❀ ❀ ❀ ❀ ❀
私が子供の頃は地元の山のてっぺんに登ることはなかったように思います
自分たちの足で行けるところは限られていましたからね
と言うより山登りをしたいなんて思わなかったですね
親と焚物かるいがやっとでしたね、、、きつかったなー
車時代が到来し道路が整備され
歩く距離が短くて、てっぺんまで行くことができるようになりましたね
尾向にも、国見山、御池とありますが
これらの山も大人になってから登りましたね
きつくてもドカッと出る汗( ; ゚Д゚)が気持ちいいのと
お弁当が美味しかったのは覚えています(´ー`* )))) あ〜ん♪

懐かしいものを見つけましたよ
扇山登山記念のペナント
(息子が小学4・5・6・年の時にもらったもの)
12/06/20
-

広大な椎葉村の一角尾向から、自然あり人間あり猫ありの日常をお届けします yamabuki810
- 20年09月
- 19年04月
- 16年05月
- 16年03月
- 16年02月
- 16年01月
- 15年11月
- 15年10月
- 15年09月
- 15年07月
- 15年06月
- 15年05月
- 15年04月
- 15年03月
- 15年02月
- 15年01月
- 14年12月
- 14年11月
- 14年10月
- 14年09月
- 14年08月
- 14年07月
- 14年06月
- 14年05月
- 14年04月
- 14年03月
- 14年02月
- 14年01月
- 13年12月
- 13年11月
- 13年10月
- 13年09月
- 13年08月
- 13年07月
- 13年06月
- 13年05月
- 13年04月
- 13年03月
- 13年02月
- 13年01月
- 12年12月
- 12年11月
- 12年10月
- 12年09月
- 12年08月
- 12年07月
- 12年06月
- 12年05月
- 12年04月
- 12年03月
- 12年02月
- 12年01月
- 11年12月



















